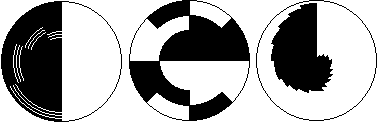白色光を明滅させて明の時に光の強さをプラス方向、或いはマイナス方向に変化させてみます。
更に明のサイクル時に変化のスピードを曲線的に変えてみます。すると変化のパターンの違いにより図のような色が現れます。
この様に元々色が無いところに色が現れる現象を主観色と呼んでいます。
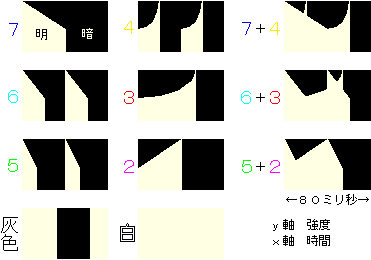
|
◇ 実験1(主観色)(フィスティンジャー) 白色光を明滅させて明の時に光の強さをプラス方向、或いはマイナス方向に変化させてみます。 更に明のサイクル時に変化のスピードを曲線的に変えてみます。すると変化のパターンの違いにより図のような色が現れます。 この様に元々色が無いところに色が現れる現象を主観色と呼んでいます。 |
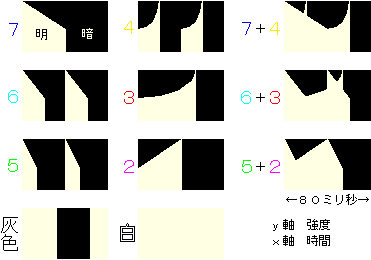
|
|
◇ 実験2(ランド効果) 図の様に色彩のある光景を2台のカメラで一方は赤フィルター、もう一方は緑フィルターをかけて二枚の白黒スライドを作ります。 それを二台のプロジェクターを使い両スライドを同時にスクリーン上に重ねて投影します。 その時に赤フィルターを使ったスライドには赤フィルターをかけ、緑フィルターを使ったスライドはそのままにして通常の白色光をあてます。 |
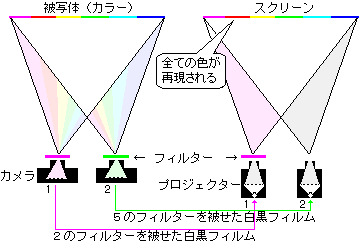
|
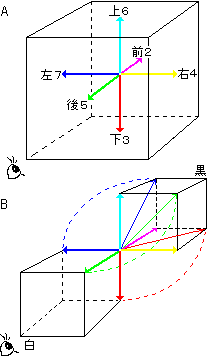
|
説明上、方向(性)と表現しましたが、これは基点から**2●〜7●のどちらの方向を向いたエネルギーかということで、仮に方向性としましたが本来の呼び方があります。
2●〜7●の光の方向を三次元的に表現すると図aのようになります。 図aの左下の3●5●7●側から見ると2●から7●の光が****左回りに並びます。 3●,5●,7●を反対側(鏡像)に畳み込むと図bの右上部分になり、光の並ぶ順序が理解し易くなります。 2●5●,3●6●,4●7●それぞれが正対しますが、これは補色の関係です。補色といわれるのはエネルギーの方向が逆向きの関係を言います。 3●,5●,7●を光で混合した場合は白になり、2●,4●,6●を色で混合した場合は黒になるという光と色の三原色の性質の違いは、図のようにそれぞれが正反対の方向を向いているためです。 |
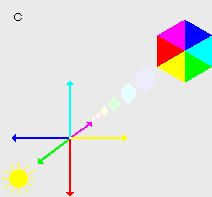
|
2●,4●,6●世界に投影された2●〜7●のそれぞれの光は六つの方向を向いている為、それがレンズ(球面)により分光され、それぞれの方向に分解されたものが六角形のハレーションとなって現れる訳です。
これは方向性が目に見える形になって現れたもので、この2●4●6●空間の平面上に投影されたものは*369のマークなのです。 |
| 右図は白黒のパターンだけで色が現れる簡単な例です。白地に斜線を引いただけのものですが、斜線の白地の部分に何やらもやもやとした色が現れるのは、眼の微動により方向性を感知しているからです。 |
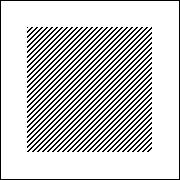
|
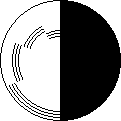
| 左図はベンハムのコマ(色々なパターンがある)と言われ、コマにして回すと色が現れます。実験1の光の明滅の代わりに回転により明暗(白黒)を切り替えます。模様は波形の違いと同様の意味を持っています。 |
「錯覚のワンダーランド」 鈴木光太郎 (関東出版社)これらは、あくまでも一つの推論です。目や脳の働き等の一部の説明及び実験以外は本などに掲載されていません。無論二つの実験に関する理論だった説明は一切なされていません、ハレーションについても同様です。
「ハテ・なぜだろうの物理学3」 j.ウオーカー 戸田盛和 他訳 (培風館)、他。
|
2●4●6●(3●)と3●5●7●(6●)のワンセットで、この物質世界の光は***36(ミロク)の光で出来ています。 図aの立方体は八個に分解でき、図bはその内の二つですから、これは全体の25%に相当します。***エゼキエル書の四つの生き物の一つ、また光の計算の***六段分、個性のエネルギーと同じ25%です。 面白い事に宇宙の物質分子中ヘリューム分子が占める質量の割合が宇宙全質量の丁度25%で、原子生成以来この比率は変わらないそうです。 |