| ◎ | 371 |
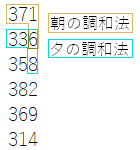
|
左図は朝と夕の調和法の構造的な違いを、枠で囲い示しています。 |
| ○ | 336 ←(前の“光”) | ||
| 358 ←(後ろの“光”) | |||
| 382 | |||
| 369 | |||
| 314 |
| ◎ | 371 |
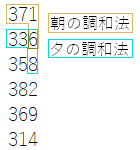
|
左図は朝と夕の調和法の構造的な違いを、枠で囲い示しています。 |
| ○ | 336 ←(前の“光”) | ||
| 358 ←(後ろの“光”) | |||
| 382 | |||
| 369 | |||
| 314 |
| ◎ | 314 |
| ○ | 393 ←(前の“光”) |
| 336 ←(後ろの“光”) |
| 渡辺泰男が“光”の探求を始めてから17年後にようやく発表した、より未分化(原始的=精神世界で言うところの高次元)な***潜在意識 第1層〜第2層(**光子体)に働きかける 画期的な調和法です。彼は「人が“光”を求めて来た時、ぐだぐだと御託(理論)を並べる必要はありません。第一の調和法と第二、*第三の調和法を伝えるだけで結構です」と言い切っています。 |